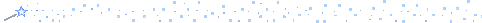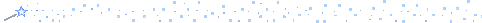
Photo by Onda
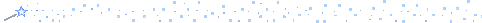
あらすじ・・・日本の花火を「世界」のランクまで高めたことで叙勲された、 長野県茅野市の田村仁三郎氏の生涯を描く、事実に基づいた小説。
 本文より(原文のまま)・・・ず、どどんと打ち揚がるときの音。この腹にひびく
音がまた、コタえられない。咲いた。みごとに咲いたとみたとたんに、どよめきが
くる。「あ、きれい!」という何万、何十万の観衆の嘆声が、どよめきとなって
つたわるのだ。観衆の感嘆する声々に、”花火師みょうり”を感じてしまう。
「どうだ。おれのつくった玉だぞ」と、胸を張りたくなる。<今度は、もっともっと
、いい玉つくってやるぜ>次回に思いをこめて、いっそう工夫を凝らす、はげみともなる。
けれど、手間ヒマかけてつくっても、つかの間に消えてしまう代物。華麗に咲いた
花は、数秒ともたない、まことに短命に果てる宿命にあるのだ。
花火師は、そうした”火の作品”を空に描きだすのではないか。
画家ならキャンバスに描いて、作品はかぎりなく年月を越えて残りつづける。
自作に、誇らしくサインもできる。それにひきかえ、花火師はどうだろう。
”火の作品”が、どんなに美しく、芸術的な出来映えであっても、あとに残らない。
年月を越えるどころか、数秒と空にとどめることもできはしない。
自作のサインを、空に記すこともかなわないのだ。たとえ「名人」だとしても、
観衆にその名が知れわたることは望めない、とくる。花火師はそれでも、
「この一発」に賭ける。花火が咲いて、消えるとき、”苦労も昇華”した満足感がくる。
十日も二十日もかけてつくった玉が、一瞬に消えたというのに・・・。
これっぽっちも、「むなしい苦労」とも思いはしない。花火を打ち揚げることを
、花火師独特の用語では、「消費」という。そう。「消費」して満足だ。
決してはかなく、むなしい消失、消滅といった気はしない。
本文より(原文のまま)・・・ず、どどんと打ち揚がるときの音。この腹にひびく
音がまた、コタえられない。咲いた。みごとに咲いたとみたとたんに、どよめきが
くる。「あ、きれい!」という何万、何十万の観衆の嘆声が、どよめきとなって
つたわるのだ。観衆の感嘆する声々に、”花火師みょうり”を感じてしまう。
「どうだ。おれのつくった玉だぞ」と、胸を張りたくなる。<今度は、もっともっと
、いい玉つくってやるぜ>次回に思いをこめて、いっそう工夫を凝らす、はげみともなる。
けれど、手間ヒマかけてつくっても、つかの間に消えてしまう代物。華麗に咲いた
花は、数秒ともたない、まことに短命に果てる宿命にあるのだ。
花火師は、そうした”火の作品”を空に描きだすのではないか。
画家ならキャンバスに描いて、作品はかぎりなく年月を越えて残りつづける。
自作に、誇らしくサインもできる。それにひきかえ、花火師はどうだろう。
”火の作品”が、どんなに美しく、芸術的な出来映えであっても、あとに残らない。
年月を越えるどころか、数秒と空にとどめることもできはしない。
自作のサインを、空に記すこともかなわないのだ。たとえ「名人」だとしても、
観衆にその名が知れわたることは望めない、とくる。花火師はそれでも、
「この一発」に賭ける。花火が咲いて、消えるとき、”苦労も昇華”した満足感がくる。
十日も二十日もかけてつくった玉が、一瞬に消えたというのに・・・。
これっぽっちも、「むなしい苦労」とも思いはしない。花火を打ち揚げることを
、花火師独特の用語では、「消費」という。そう。「消費」して満足だ。
決してはかなく、むなしい消失、消滅といった気はしない。
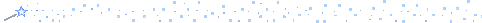
あらすじ・・・恋に破れた25歳のOL、祥子は放心の日々のなかでふとしたことから 女花火師・立花薫を知り花火の世界にのめり込む。そして薫の家に下働きとして住み込み 、慣れない仕事にとまどいながらも新たな人生を歩みはじめる。
やがて耳を聾せんばかりの音と共に、たて続けに大輪の花が頭上に開いた。見物人から
、歓声が上がった。(中略)見物人たちは、矢つぎ早に打揚げられる花火に、声もなく
見とれている。早打ちが終わって、一瞬間があくと、ようやくわれにかえった人々の間に
どよめきが起きる。そこへ、大型の花火が、一発高く打揚げられる。色の異なる三重の
花が重なって開き、それが同時に二度三度と色を変え、最後に露のように光って消える。
それに見とれている間もなく、尾を引きながら竜のように天空に駆け昇る花火、あるいは
小花を散らしながら上昇する花火が、つぎつぎに開く。 本文より・・・薫は、連ねた筒に沿って柔軟に体を移動しながら、緩急をつけて火を
つけてゆく。頭の真上で百花繚乱と開く花火よりも、祥子は薫の動きに目を据えている。
一瞬、音が止み、あたりは静まり返る。観客の歓声も止む。と、突然息をもつかせぬ
早さで、最後の数十本の筒から花火が打揚げられた。終わるとしばらくは声のなかった
観客から、歓声と拍手が湧いた。
本文より・・・薫は、連ねた筒に沿って柔軟に体を移動しながら、緩急をつけて火を
つけてゆく。頭の真上で百花繚乱と開く花火よりも、祥子は薫の動きに目を据えている。
一瞬、音が止み、あたりは静まり返る。観客の歓声も止む。と、突然息をもつかせぬ
早さで、最後の数十本の筒から花火が打揚げられた。終わるとしばらくは声のなかった
観客から、歓声と拍手が湧いた。
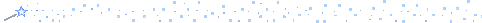
あらすじ・・・信州の安曇野に移り住んだ筆者が、自分の周囲の人々の生活を「よそ者」 の視点から描いたエッセイ集。念願かなって花火師の仕事場に、取材と称してもぐりこん だ筆者だが・・・。
何とという感動だ。伏せてなどいられるものではない。温泉郷の場合は一晩
に四百万円が夜空に消え、大阪あたりでは一億円とか二億円が闇に散るそうだが、少しも
もったいないとは思わない。花火は遠くで見るものではないとつくづく思う。花火は真下
で見るものだ。(中略)
四百万円分の花火が終わったあと、私たちはしばらくのあいだぼんやりしていた。感動は
いつまでもつづいた。そして、ふたたび大勢の見物人のなかへ身を投じたとき、ひといきれや
、足音や、話し声や、クルマの音に囲まれて、いっぺんにうんざりしてしまった。ふとこんな
ことを考えた。ひょっとするとあの花火は、見物人のためにではなく、花火師自身のために
打ち上げられたのではないだろうか、と。だから、見物人の眼に映ったのは実は花火の出がらし
ではなかっただろうか。(中略) 本文より・・・そしていよいよ無数の火の粉が夜の真ん中を引き裂くと、町中の
人間が「アー、アー」というため息にも似た哀しい声をあげ、光のあとからやってくる爆発音が
窓ガラスを震わせ、更に胃袋を圧迫すると、瞼にくっきりやきついた残像をしつこく追い求め、
それからハッとわれに返り、またもや性的ともいえるあの長い声を「アー、アー」ともらすのだった。(中略)
本文より・・・そしていよいよ無数の火の粉が夜の真ん中を引き裂くと、町中の
人間が「アー、アー」というため息にも似た哀しい声をあげ、光のあとからやってくる爆発音が
窓ガラスを震わせ、更に胃袋を圧迫すると、瞼にくっきりやきついた残像をしつこく追い求め、
それからハッとわれに返り、またもや性的ともいえるあの長い声を「アー、アー」ともらすのだった。(中略)
花火師たちの顔はどれもいい顔だった。スカッとしていた。
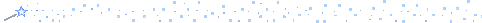
あらすじ・・・女花火師、伊奈子に思いをよせる、秩父の織元の主人、仁科。 仁科は地元温泉郷振興のために始めた、「音楽花火」の成功と伊奈子への愛 の成就に全てをかける。
彼女の説明する、花火の製造過程の愚かしいまでの手間と、一瞬大空に咲いて消滅していく
結果との落差は人生そのもののようで私には興味深いものだった。私は次々に質問した。 本文より・・・その年の夜祭は私もハッキリ覚えている。夜半から雪になり、打ち上げ
られる花火は一色ごとに降る雪に響き合い、雪片のひとつひとつを七色に染め上げた。
一瞬結晶した点描のパステル画はみるみる闇の水に流れて消える。消えたと思うと
別の点描が天に弾けた。それはこの世のものとも思えぬ万華鏡であった。見上げる
人々は氷柱と固まり、炸裂音は太鼓のリズムと呼応して氷柱たちの胸をかきむしった。
あの夜の万華鏡が仁科を捕らえた。それを荒くれ男に交じって指揮する伊奈子は、天女
のようだった、と仁科は言った。(中略)
本文より・・・その年の夜祭は私もハッキリ覚えている。夜半から雪になり、打ち上げ
られる花火は一色ごとに降る雪に響き合い、雪片のひとつひとつを七色に染め上げた。
一瞬結晶した点描のパステル画はみるみる闇の水に流れて消える。消えたと思うと
別の点描が天に弾けた。それはこの世のものとも思えぬ万華鏡であった。見上げる
人々は氷柱と固まり、炸裂音は太鼓のリズムと呼応して氷柱たちの胸をかきむしった。
あの夜の万華鏡が仁科を捕らえた。それを荒くれ男に交じって指揮する伊奈子は、天女
のようだった、と仁科は言った。(中略)
「打ち上げの割り物で腐心するのはなに?」
「どう消すか、ということでしょうか」
「どう消す・・・・?」
「大輪の菊や牡丹でも同時に歯切れよく消えないと決して美しくありません。
音楽花火も
音をいかに消すかが勝負です」
「今年歯切れが良かったのは、じゃ、消し方がよかったんだ」
「はい、打ち上げた笛を、鳴っている間に壊しました。以前から判っていたのですが、壊すのに
また音が出てうまくいかなかったのです。」
「なるほど、今回はそれができた・・・」
「花火屋はすぐ火薬で壊すことを考えてしまいます。それがいけなかったのです」